ホーム>原子力人材育成プログラム>実施校の紹介および事業成果概要・評価
原子力人材育成プログラムとは  |
文部科学省事業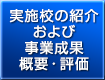 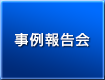 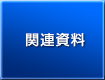 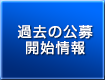 |
|
年度ごとに、各実施校と成果概要を紹介します。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.平成24年度原子力人材育成プログラム |
| 1-① 文部科学省事業 |
| (1)原子力研究基盤整備プログラム (3件) (プログラム概要は、こちら) |
| 実施校名 | 実施年度 | 事業概要 | 成果評価 評価方法はこちら |
| 京都大学 | H22~H24 | 京都大学原子炉実験所における原子力教育研究基盤の整備 [PDF:398KB] | 評価【A】 評価コメント |
| 東京工業大学 | H22~H24 | カリキュラム充実による原子力大学院教育基盤の整備 [PDF:398KB] | 評価【B】 評価コメント |
| 東京大学 | H22~H24 | 国際舞台で活躍出来る原子力グローバルリーダー教育プログラム [PDF:398KB] | 評価【B】 評価コメント |
| 2.平成23年度原子力人材育成プログラム |
| 2-① 文部科学省事業 |
| (1)原子力研究促進プログラム (7件) |
| 実施校名 | 実施年度 | 事業概要 | 成果評価 評価方法はこちら |
| 熊本高等専門学校 | H22~H23 | 講義や放射線測定実験の体験型教育等による原子力人材の育成 [PDF:398KB] | 評価【B】 評価コメント |
| 富山高等専門学校 | H22~H23 | 専門レベルを考慮した全学科を対象とする原子力人材育成プログラム[PDF:321KB] | 評価【A】 評価コメント |
| 阿南工業高等専門学校 | H22~H23 | 四国内の高等専門学校と企業の連携に基づく原子力人材育成 [PDF:613KB] | 評価【B】 評価コメント |
| 茨城大学 | H22~H23 | 地域連携を生かした原子力導入教育と大学院実習教育の実践 [PDF:271KB] | 評価【B】 評価コメント |
| 東海大学 | H22~H23 | 原子力マイスター育成のための実務と教育のブリッジプログラム [PDF:275KB] | 評価【B】 評価コメント |
| 石川工業高等専門学校 | H22~H23 | 地元原子力関連企業の協力による継続的な原子力教育の実施 [PDF:881KB] | 評価【B】 評価コメント |
| 福井工業高等専門学校 | H22~H23 | 現場研修とものづくり実践による原子力・放射線基礎教育 [PDF:285KB] | 評価【B】 評価コメント |
| (2)原子力コア人材育成プログラム (4件) |
| 実施校名 | 実施年度 | 事業概要 | 成果評価 評価方法はこちら |
| 早稲田大学 | H22~H23 | 理工学術院の特色を踏まえた原子力教育プログラムの開発整備 [PDF:628KB] | 評価【B】 評価コメント |
| 静岡大学 | H22~H23 | 原子力安全を支える原子力・放射線専門家育成プログラム [PDF:418KB] | 評価【B】 評価コメント |
| 八戸工業高等専門学校 | H22~H23 | 地域資源を活かした原子力人材育成プログラム [PDF:232KB] | 評価【A】 評価コメント |
| 東北大学 | H22~H23 | 実践的保全工学の理解に基づく学際的人材育成教育システムの構築 [PDF:513KB] | 評価【B】 評価コメント |
| (3)原子力研究基盤整備プログラム (3件) |
| 実施校名 | 実施年度 | 事業概要 |
| 京都大学 | H22~H24 | 京都大学原子炉実験所における原子力教育研究基盤の整備 [PDF:347KB] |
| 東京工業大学 | H22~H24 | カリキュラム充実による原子力大学院教育基盤の整備 [PDF:455KB] |
| 東京大学 | H22~H24 | 国際舞台で活躍出来る原子力グローバルリーダー教育プログラム [PDF:308KB] |
| 2-② 経済産業省事業 |
| (1)原子力人材育成プログラム補助事業 (6件) |
| 実施機関名 | 実施年度 |
| 福井工等専門学校、静岡大学、東京大学、八戸工業大学、東北大学、(株)東芝 | H23 |
| (2)原子力関係人材育成事業 (3件) |
| 実施機関名 | 実施年度 |
| (財)若狭湾エネルギー研究センター、関西電力(株)関西電力能力開発センター、 新潟工科大学 | H23 |
| 3.平成22年度原子力人材育成プログラム |
| 3-① 文部科学省事業 |
| (1)原子力研究促進プログラム (7件) |
| 実施校名 | 実施年度 | 事業概要 |
| 熊本高等専門学校 | H22~H23 | 講義や放射線測定実験の体験型教育等による原子力人材の育成[PDF:311KB] |
| 富山高等専門学校 | H22~H23 | 専門レベルを考慮した全学科を対象とする原子力人材育成プログラム[PDF:250KB] |
| 阿南工業高等専門学校 | H22~H23 | 四国内の高等専門学校と企業の連携に基づく原子力人材育成 [PDF:507KB] |
| 茨城大学 | H22~H23 | 地域連携を生かした原子力導入教育と大学院実習教育の実践 [PDF:268KB] |
| 東海大学 | H22~H23 | 原子力マイスター育成のための実務と教育のブリッジプログラム [PDF:363KB] |
| 石川工業高等専門学校 | H22~H23 | 地元原子力関連企業の協力による継続的な原子力教育の実施 [PDF:668KB] |
| 福井工業高等専門学校 | H22~H23 | 現場研修とものづくり実践による原子力・放射線基礎教育 [PDF:257KB] |
| (2)原子力コア人材育成プログラム (9件) |
| 実施校名 | 実施年度 | 事業概要 | 成果評価 評価方法はこちら |
| 釧路工業高等専門学校 | H21~H22 | 原子力マインドを育てる実践型原子力・放射線教育プログラム [PDF:376KB] | 評価【B】 評価コメント |
| 呉工業高専専門学校 | H21~H22 | ものづくり教育をベースとした原子力人材育成プロジェクト [PDF:711KB] | 評価【B】 評価コメント |
| 東京学芸大学 | H21~H22 | 小・中学校教員養成課程のための原子力教育用カリキュラムと教材の開発およびその活用[PDF:515KB] | 評価【A】 評価コメント |
| 長岡技術科学大学 | H21~H22 | 基盤的工学知識とコミュニケーション能力を兼備した原子力システム安全・保全工学技術者育成プログラム構築 [PDF:1.08MB] | 評価【B】 評価コメント |
| 津山工業高等専門学校 | H21~H22 | 地域連携・早期一貫教育による低線量放射線・原子力に関わる実践的コア人材育成[PDF:189KB] | 評価【B】 評価コメント |
| 実施校名 | 実施年度 | 事業概要 |
| 早稲田大学 | H22~H23 | 理工学術院の特色を踏まえた原子力教育プログラムの開発整備 [PDF:400KB] |
| 静岡大学 | H22~H23 | 原子力安全を支える原子力・放射線専門家育成プログラム[PDF:508KB] |
| 八戸工業高等専門学校 | H22~H23 | 地域資源を活かした原子力人材育成プログラム[PDF:359KB] |
| 東北大学 | H22~H23 | 実践的保全工学の理解に基づく学際的人材育成教育システムの構築 |
| (3)原子力研究基盤整備プログラム (3件) |
| 実施校名 | 実施年度 | 事業概要 |
| 京都大学 | H22~H24 | 京都大学原子炉実験所における原子力教育研究基盤の整備 [PDF:283KB] |
| 東京工業大学 | H22~H24 | カリキュラム充実による原子力大学院教育基盤の整備 [PDF:376KB] |
| 東京大学 | H22~H24 | 国際舞台で活躍出来る原子力グローバルリーダー教育プログラム [PDF:616KB] |
| 3-② 経済産業省事業(詳細は、平成22年度経済産業省事業による) |
| (1)原子力総合技術プログラム (7件) |
| 実施校名 | 実施年度 | 事業概要 |
| 近畿大学 | H22 | 近大原子炉を用いた実験実習と原子炉実習に基づく教育システムの整備 |
| 東京都市大学 | H22 | 総合的・実践的教育のためのカリキュラム開発及び実験実習等 |
| 京都大学 | H22 | 全国の学部学生・大学院生を対象とする原子炉・原子力実験 |
| 室蘭工業大学 | H22 | 拠点ネットワーク活用による原子力材料人材育成プログラムの強化 |
| 東京工業大学 | H22 | 核燃料サイクル工学の実践的教育システムの構築 |
| 九州大学 | H22 | 問題解決能力を育てる原子力総合教育カリキュラムの構築 |
| 北海道大学 | H22 | 大学と企業の研究設備を活用した炉心伝熱流動実習教育と教材作成 |
| (2)国際原子力人材プログラム (2件) |
| 実施校名 | 実施年度 | 事業概要 |
| 東京工業大学 | H22 |
国際原子力人材育成ネットワーク基盤の構築 |
| 東京大学 | H22 |
英語版『原子力教科書シリーズ』の作成 |
| (3)原子力地域人材プログラム (4件) |
| 実施校名 | 実施年度 | 事業概要 |
| 福井工業高等専門学校 | H22 | 高専の一貫教育体制に即した原子力関連教育の実践 |
| 福島工業高等専門学校 | H22 | 高専・大学・企業・自治体との複合型連携体験学習による原子力人材育成 |
| 八戸工業大学 | H22 | エネルギー拠点としての地域に根ざした原子力基盤人材育成計画 |
| 福井大学 | H22 | 平成22年度 敦賀「原子力」夏の大学 |
| (4)原子力の基盤技術分野強化プログラム (3件) |
| 実施校名 | 実施年度 | 事業概要 |
| 京都大学 | H19~H21 H22:事業遅延 |
生体影響に視点を置いた新しい放射線防護体系の構築に関する技術開発 |
| 北海道大学 | H20~H22 | 原子力施設用配管の耐震尤度評価法と耐震性向上技術に関する開発 |
| 横浜国立大学 | H20~H22 | 局部減肉配管の耐震性評価と再稼働条件の明確化に向けた技術開発 |
| 4.平成21年度原子力人材育成プログラム |
| 4-① 文部科学省事業 |
| (1)原子力研究促進プログラム (17件) |
| 実施校名 | 実施年度 | 事業概要 | 成果評価 評価方法はこちら |
| 富山工業高等専門学校 | H21 | 学生の自立的な取り組みによる放射線計測システムの開発と大学での研究実習 [PDF:350KB] | 評価【B】 評価コメント |
| 山梨大学 | H21 | 大学共通教育における放射線・原子力リテラシー教育の展開 [PDF:408KB] | 評価【B】 評価コメント |
| 東海大学 | H21 | 原子力系技術者育成のための放射線取扱研修プログラム [PDF:409KB] | 評価【A】 評価コメント |
| 武蔵工業大学 (現 東京都市大学) |
H21 | 大学生のための霧箱を活用した放射線学習プログラムの開発 [PDF:458KB] | 評価【B】 評価コメント |
| 広島商船高等専門学校 | H21 | 商船高専生のための原子力教育 [PDF:412KB] | 評価【B】 評価コメント |
| 福井工業高等専門学校 | H21 | 高専生のものづくり教育としての中・高生用放射線教育教材の試作開発 [PDF:225KB] | 評価【B】 評価コメント |
| 木更津工業高等専門学校 | H21 | 一般特別研究「放射線の物理学」における原子力研究の促進 [PDF:746KB] | 評価【A】 評価コメント |
| 茨城工業高等専門学校 | H21 | 低学年の学生に対する放射線・エネルギー・原子力への興味の喚起および、高学年の学生のインターンシップや研究活動を通した原子力分野の専門教育 [PDF:176KB] | 評価【B】 評価コメント |
| 福井工業大学 | H21 | 学生が組み立てる原子燃料サイクルの実践的教育 [PDF:347KB] | 評価【C】 評価コメント |
| 石川工業高等専門学校 | H21 | 地元原子力発電所と協力した原子力教育と学生による啓蒙活動の実施 [PDF:512KB] | 評価【B】 評価コメント |
| 八代工業高等専門学校 (現 熊本高等専門学校) |
H21 | 霧箱による体験学習や実験・講義を通じた放射線・原子力教育の実施 [PDF:448KB] | 評価【B】 評価コメント |
| 名古屋大学 | H21 | 高度中性子工学実験実習プログラム [PDF:375KB] | 評価【B】 評価コメント |
| 一関工業高等専門学校 | H21 | 段階的な体験的学習を通した原子力産業の基礎的理解と問題点を含めた放射線安全の理解に対する教育プログラム [PDF:573KB] | 評価【B】 評価コメント |
| 福島工業高等専門学校 | H21 | 高専・大学・産業界連携による実習・卒業研究体験型教育の促進 [PDF:531KB] | 評価【A】 評価コメント |
| 山形大学 | H21 | 原子力安全利用のための体験型放射線学習プログラムの構築 [PDF:365KB] | 評価【B】 評価コメント |
| 詫間電波工業高等専門学校 (現 香川高等専門学校) |
H21 | 新居浜・詫間電波高専の連携による、持続的に地域の原子力産業・人材育成に貢献することを目的とした学生主体の研究体制づくり~ジグソー式開発手法導入と地元高専出身の原子力技術者らとの交流支援を通して~ [PDF:187KB] | 評価【B】 評価コメント |
| 福井大学 | H21 | 地域社会との協働による原子力の社会化を促す人材育成プロジェクト [PDF:1.4MB] | 評価【C】 評価コメント |
| (2)原子力コア人材育成プログラム (14件) |
| 実施校名 | 実施年度 | 事業概要 | 成果評価 評価方法はこちら |
| 東海大学 | H20~H21 | 高校大学連携による「萌芽段階」と「進展段階」にある学生教育のための中核的教員人材養成およびリカレントプログラムの作成 [PDF:236KB] | 評価【B】 評価コメント |
| 福井工業大学 | H20~H21 | 放射線安全専門職育成プログラム開発 [PDF:344KB] | 評価【B】 評価コメント |
| 東北大学 | H20~H21 | 実践的保全工学を担う持続的人材育成研究教育コースの構築 [PDF:351KB] | 評価【A】 評価コメント |
| 九州大学 | H20~H21 | 核燃料サイクル工学に関する実験・演習の充実 [PDF:437B] | 評価【B】 評価コメント |
| 茨城大学 | H20~H21 | 地域連携を生かした原子力人材育成大学院教育プログラムと学部における原子力導入教育の整備と実践 [PDF:450KB] | 評価【B】 評価コメント |
| 八戸工業高等専門学校 | H20~H21 | 連峰型原子力人材育成プログラム in あおもり [PDF:347KB] | 評価【A】 評価コメント |
| 北海道大学 | H20~H21 | プルサーマル・長サイクル運転対応燃料炉心管理の中核人材の育成 [PDF:310KB] | 評価【B】 評価コメント |
| 茨城大学 | H20~H21 | 原子力コア人材育成のための理学部教育プログラムの確立 [PDF:307KB] | 評価【B】 評価コメント |
| 武蔵工業大学 (現 東京都市大学) |
H20~H21 | 実践的原子力技術者育成のための教育体系の整備 [PDF:426KB] | 評価【B】 評価コメント |
| 実施校名 | 実施年度 | 事業概要 |
| 釧路工業高等専門学校 | H21~H22 | 原子力マインドを育てる実践型原子力・放射線教育プログラム [PDF:277KB] |
| 呉工業高専専門学校 | H21~H22 | ものづくり教育をベースとした原子力人材育成プロジェクト [PDF:990KB] |
| 東京学芸大学 | H21~H22 | 小・中学校教員養成課程のための原子力教育用カリキュラムと教材の開発およびその活用 [PDF:485KB] |
| 長岡技術科学大学 | H21~H22 | 基盤的工学知識とコミュニケーション能力を兼備した原子力システム安全・保全工学技術者育成プログラム構築 [PDF:617KB] |
| 津山工業高等専門学校 | H21~H22 | 地域連携・早期一貫教育による低線量放射線・原子力に関わる実践的コア人材育成 [PDF:679KB] |
| (3)原子力研究基盤整備プログラム (3件) |
| 実施校名 | 実施年度 | 事業概要 | 成果評価 評価方法はこちら |
| 東北大学 | H19~H21 | 大学所有のRI施設における計測・分析装置を強化充実して核燃料サイクル関連の学生実験を強化することにより、六ヶ所サイトのニーズに答える戦略的な教育研究活動を一層推進し、先進バックエンド研究を展開。 [PDF:258KB] | 評価【A】 評価コメント |
| 京都大学 | H19~H21 | 教育目的で使用する中性子線源の開発のための施設整備。JRR-4、HANARO(韓国原子力研究所)を含むKUR以外の施設・設備での研究・教育の推進。外国人研究者招聘による国際的研究・教育拠点整備。 [PDF:356KB] | 評価【B】 評価コメント |
| 東京大学 | H19~H21 | 原子力教育カリキュラムの充実(実験、実習を含む)。外部講師による講義の実施。国際的視野を有する教育の充実。原子力の長期ニーズに即したカリキュラム内容の改善・向上。高度原子力技術者としての質とスキルの向上を修了後にも継続して実施できる環境の整備。 [PDF:206KB] | 評価【A】 評価コメント |
| 4-② 経済産業省事業(詳細は、平成21年度経済産業省事業による) |
| (1)原子力教育支援プログラム (8件) |
| 実施校名 | 実施年度 | 事業概要 |
| 九州大学 | H21 | 原子炉物理及び放射線計測・安全学に関する実験演習と補助教材の開発 |
| 東京工業大学 | H21 | 実践的核燃料サイクル工学実験教育カリキュラムの構築 |
| 大阪大学 | H21 | 遠隔地でも利用可能なユビキタス原子力実践教育システムの構築 |
| 武蔵工業大学 (現 東京都市大学) |
H21 | 原子力の基礎教育・実践的教育のためのカリキュラム開発等 |
| 静岡大学 | H21 | 原子力発電所と連携した放射線管理実習プログラムの構築 |
| 東京大学 | H21 | 最高度の原子力専門職教育の構築と最新知見の集大成 |
| 室蘭工業大学 | H21 | 原子炉構造材料の生産・保全に係る人材育成プログラムの構築 |
| 北海道大学 | H21 | 原子力基礎と保全工学基礎統合強化プログラムによる原子力人材育成教育 |
| (2)チャレンジ原子力体感プログラム (10件) |
| 実施校名 | 実施年度 | 事業概要 |
| 東京工業大学 | H21 | IAEA国際インターンシップ及び米国原子力学会研究発表派遣 |
| 九州大学 | H21 | 海外での実践的な実験・発表演習を活用した国際的人材の育成 |
| 京都大学 | H21 | 京大学生・学院生及び全国大学院生を対象とする原子炉・原子力実験 |
| 東北大学 | H21 | 生きた原子力を体感するための統合・実践研修プログラム |
| 東京大学 | H21 | 原子力関連施設見学、実験・実習及び海外大学サマースクール |
| 近畿大学 | H21 | 近畿大学原子炉を用いた体験・実践型の実習教育研修会 |
| 函館工業高等専門学校 | H21 | 複合的な視点から原子力を体感するチャレンジプログラム |
| 福井大学 | H21 | 平成21年度敦賀「原子力」夏の大学 |
| 八戸工業大学 | H21 | 地域に立脚したチャレンジ原子力体感プログラム |
| 旭川工業高等専門学校 | H21 | 北海道道北圏での原子力施設に対する理解を深めるチャレンジ原子力体感プログラム |
| (3)原子力の基盤技術分野強化プログラム (8件) |
| 実施校名 | 実施年度 | 事業概要 |
| 東京大学 | H19~H21 | 蒸気乾燥器の流体関連振動に関する技術開発 |
| 東京大学 | H19~H21 | 機構論に立脚したより安全なハフニウム板型制御棒の開発 |
| 京都大学 | H19~H21 | 圧力容器溶接部の健全性評価法の規格・基準化に関する技術開発 |
| 大阪大学 | H19~H21 | ステンレス鋼レーザ溶接部の高信頼性化に関する研究 |
| 東北大学 | H19~H21 | 高Ni合金の高温水中SCC※機構解明と耐SCC成分設計に関する基礎的研究 ※SCC(応力腐食割れ) |
| 京都大学 | H19~H21 | 生体影響に視点を置いた新しい放射線防護体系の構築に関する技術開発 |
| 北海道大学 | H20~H22 | 原子力施設用配管の耐震尤度評価法と耐震性向上技術に関する開発 |
| 横浜国立大学 | H20~H22 | 局部減肉配管の耐震性評価と再稼働条件の明確化に向けた技術開発 |
| 5.平成20年度原子力人材育成プログラム |
| 5-① 文部科学省事業 |
| (1)原子力研究促進プログラム (11件) |
| 実施校名 | 実施年度 | 事業概要 |
| 東海大学 | H20 | 原子力系技術者育成のための放射線取扱研修プログラム [PDF:299KB] |
| 福井工業大学 | H20 | 学生が組み立てる原子燃料サイクルの実践的教育 [PDF:313KB] |
| 山形大学 | H20 | 原子力安全利用のための体験型放射線学習プログラムの構築 [PDF:270KB] |
| 静岡大学 | H20 | 学生課題創成型放射線管理実習プログラム [PDF:218KB] |
| 東京工業大学 | H20 | 大学院学生によるわかりやすい一般向け原子力・放射線教材の開発 [PDF:242KB] |
| 富山工業高等専門学校 | H20 | 学生の自立的な取り組みによる放射線計測システムの開発と大学での研究実習 [PDF:297KB] |
| 石川工業高等専門学校 | H20 | 実践的技術者養成を目指した地元原子力発電所との協同教育体制の構築 [PDF:378KB] |
| 福井工業高等専門学校 | H20 | 体験学習を組み込んだ原子力・放射線基礎教育の促進 [PDF:265KB] |
| 松江工業高等専門学校 | H20 | 体験学習を通じた実践的原子力人材の育成 [PDF:521KB] |
| 八代工業高等専門学校 (現 熊本高等専門学校) |
H20 | 実験・講義を通じた放射線・原子力教育の実施、および地域連携活動等による原子力等の基礎知識・情報の提供 [PDF:443KB] |
| 茨城工業高等専門学校 | H20 | 原子力発電所に隣接する高専における低学年の学生に対する原子力・放射線への興味の喚起・涵養と、上級生に対する原子力分野の専門教育の実施 [PDF:186KB] |
| (2)原子力コア人材育成プログラム (12件) |
| 実施校名 | 実施年度 | 事業概要 |
| 東海大学 | H20~H21 | 高校大学連携による「萌芽段階」と「進展段階」にある学生教育のための中核的教員人材養成およびリカレントプログラムの作成 [PDF:363KB] |
| 福井工業大学 | H20~H21 | 放射線安全専門職育成プログラム開発 [PDF:283KB] |
| 東北大学 | H20~H21 | 実践的保全工学を担う持続的人材育成研究教育コースの構築 [PDF:273KB] |
| 九州大学 | H20~H21 | 核燃料サイクル工学に関する実験・演習の充実 [PDF:450KB] |
| 茨城大学 | H20~H21 | 地域連携を生かした原子力人材育成大学院教育プログラムと学部における原子力導入教育の整備と実践 [PDF:467KB] |
| 茨城大学 | H20~H21 | 原子力コア人材育成のための理学部教育プログラムの確立 [PDF:316KB] |
| 北海道大学 | H20~H21 | プルサーマル・長サイクル運転対応燃料炉心管理の中核人材の育成 [PDF:273KB] |
| 武蔵工業大学 (現 東京都市大学) |
H20~H21 | 実践的原子力技術者育成のための教育体系の整備 [PDF:257KB] |
| 八戸工業高等専門学校 | H20~H21 | 連峰型原子力人材育成プログラム in あおもり [PDF:414KB] |
| 福井大学 | H20~H21 | 安全と共生を支える文理融合・地域協働の原子力人材育成プロジェクト [PDF:705KB] |
| 弘前大学 | H20~H21 | 原子力を理解し支える機械技術者養成のための材料工学教育 [PDF:189KB] |
| 呉工業高等専門学校 | H20~H21 | ものづくり教育をベースとした原子力人材育成プロジェクト [PDF:530KB] |
| (3)原子力研究基盤整備プログラム (3件) |
| 実施校名 | 実施年度 | 事業概要 |
| 東北大学 | H19~H21 | 大学所有のRI施設における計測・分析装置を強化充実して核燃料サイクル関連の学生実験を強化することにより、六ヶ所サイトのニーズに答える戦略的な教育研究活動を一層推進し、先進バックエンド研究を展開。 [PDF:208KB] |
| 京都大学 | H19~H21 | 教育目的で使用する中性子線源の開発のための施設整備。JRR-4、HANARO(韓国原子力研究所)を含むKUR以外の施設・設備での研究・教育の推進。外国人研究者招聘による国際的研究・教育拠点整備。 [PDF:388KB] |
| 東京大学 | H19~H21 | 原子力教育カリキュラムの充実(実験、実習を含む)。外部講師による講義の実施。国際的視野を有する教育の充実。原子力の長期ニーズに即したカリキュラム内容の改善・向上。高度原子力技術者としての質とスキルの向上を修了後にも継続して実施できる環境の整備。 [PDF:200KB] |
| 5-② 経済産業省事業(詳細は、平成20年度経済産業省事業による) |
| (1)原子力教育支援プログラム (10件) |
| 実施校名 | 実施年度 | 事業概要 |
| 愛媛大学 | H20 | 放射線および放射能について正しく理解促進を図るための教育プログラムの開発 |
| 武蔵工業大学 (現 東京都市大学) |
H20 | 原子力安全工学科の新設にかかる教育体系プログラム整備 |
| 京都大学 | H20 | 学生用実習・実験テキストおよび教員・大学院生の実験・実習指導要領書の開発 |
| 大阪大学 | H20 | 原子力実践教育システムの構築、教育用シミュレータの開発・利用、インターネット原子炉シミュレーションシステムの整備 |
| 東京工業大学 | H20 | 核燃料サイクル工学実験を通したカリキュラムの改善および充実 |
| 福井工業大学 | H20 | 放射線コミュニケーター育成の実践的カリキュラム開発および講師または高学年生による低学年生への教育 |
| 九州大学 | H20 | 原子炉物理・放射線計測および安全学に関する実験・演習の充実 |
| 室蘭工業大学 | H20 | 原子力発電システムの生産・保全に係る教育プログラムの構築 |
| 東京大学 | H20 | 原子力専攻科目の体系的教科書教材の作成およびラーニングアドバイザによる教育 |
| 北海道大学 | H20 | 初等炉物理教材の開発、放射線理解促進のための技術習得、保全工学基礎強化プログラムの開発 |
| (2)チャレンジ原子力体感プログラム (9件) |
| 実施校名 | 実施年度 | 事業概要 |
| 大阪大学 | H20 | 原子力国際インターンシップ、原子力メンター制度、原子力PBリーダー養成制度、原子力実習教育の実施 |
| 東京大学 | H20 | 原子力関連施設における見学、実験・実習および海外大学におけるサマースクール等の集中講義への参加 |
| 京都大学 | H20 | 全国共同利用研究所である京都大学原子炉実験所の施設を利用した、京都大学を含む全国12大学における実験教育の実施 |
| 東京工業大学 | H20 | 研究炉を用いた原子炉物理の実験・実習、国際インターンシップおよび、日本原子力学会の大会への学生派遣等 |
| 近畿大学 | H20 | 近畿大学の原子炉を利用した原子炉運転等の体験、実践型の実習、研修会の実施 |
| 武蔵工業大学 (現 東京都市大学) |
H20 | 原子炉運転実習、原子力産業施設見学、日本原子力学会への学生派遣 |
| 福井大学 | H20 | 原子力関連知識・技術実習の場である「敦賀原子力夏の大学」の実施 |
| 八戸工業大学 | H20 | 原子力発電所、再処理施設等での研修及び実習、研究施設における材料試験等の実習、また各実習に関する事前学習の実施 |
| 函館工業高等専門学校 | H20 | 原子力産業企業等の施設見学、インターンシップの実施 |
| (3)原子力の基盤技術分野強化プログラム (8件) |
| 実施校名 | 実施年度 | 事業概要 |
| 東京大学 | H19~H21 | 蒸気乾燥器の流体関連振動に関する技術開発 |
| 東京大学 | H19~H21 | 機構論に立脚したより安全なハフニウム板型制御棒の開発 |
| 京都大学 | H19~H21 | 圧力容器溶接部の健全性評価法の規格・基準化に関する技術開発 |
| 大阪大学 | H19~H21 | ステンレス鋼レーザ溶接部の高信頼性化に関する研究 |
| 東北大学 | H19~H21 | 高Ni合金の高温水中SCC※機構解明と耐SCC成分設計に関する基礎的研究 ※SCC(応力腐食割れ) |
| 京都大学 | H19~H21 | 生体影響に視点を置いた新しい放射線防護体系の構築に関する技術開発 |
| 北海道大学 | H20~H22 | 原子力施設用配管の耐震尤度評価法と耐震性向上技術に関する開発 |
| 横浜国立大学 | H20~H22 | 局部減肉配管の耐震性評価と再稼働条件の明確化に向けた技術開発 |
| 6.平成19年度原子力人材育成プログラム |
| 6-① 文部科学省事業 |
| (1)原子力研究促進プログラム (12件) |
| 実施校名 | 実施年度 | 事業概要 |
| 東海大学 | H19 | 第1種放射線取り扱い主任者の資格取得を目的とした放射線測定・放射性物質取り扱いの基礎実験。学生による特別課題の設定・実験。 [PDF:206KB] |
| 東京大学 | H19 | 原子炉から取り出した中性子ビーム利用装置の設計・製作・性能評価による研究者の育成。 [PDF:194KB] |
| 東北大学 | H19 | ウラン取り扱いの基礎的実験。技術の習得とウランの溶液科学、固体力学への理解を深める。[PDF:200KB] |
| 東京工業大学 | H19 | 学生による、小中高生・一般人向けの原子力・放射線に関する実験・実演用教材の開発。[PDF:233KB] |
| 武蔵工業大学 (現 東京都市大学) |
H19 | 学生の参加による廃炉後の設備を利用した実体感型原子炉シミュレータの構築。 [PDF440KB] |
| 大阪府立大学 | H19 | 大学所有の施設・装置を活用した実験・実習による、放射線に関する幅広い知識の習得。 [PDF:144KB] |
| 松江工業高等専門学校 | H19 | 原子力発電所の見学・インターン。資格取得に関する講義・講演の開催。学生による卒業研究の実施。 [PDF:204KB] |
| 富山工業高等専門学校 | H19 | 原子力関連講義の実施。放射線測定システムの設計・製作。原子力施設の見学。学会参加。 [PDF:217KB] |
| 福井工業高等専門学校 | H19 | 卒業研究等において、一般市民や小・中学生対象のサイエンスフェアや近隣小・中学校で活用することも可能な放射線検出器を製作し、放射線測定を行う。 [PDF:193KB] |
| 釧路工業高等専門学校 | H19 | 原子力産業全般に関する講義、原子力関連施設の見学・インターンの実施。学生が主体となった市民対象の原子力発電に関するタウンミーティング開催。 [PDF:160KB] |
| 阿南工業高等専門学校 | H19 | 新居浜工業高専、詫間電波工業高専と連携して、学校所有のシミュレータも活用した原子力関連講義を実施。原子力関連施設の見学・研修。 [PDF:139KB] |
| 茨城工業高等専門学校 | H19 | 自然放射線の簡易測定。原子力関係施設の見学。原子力プラント構造材料の強度評価に関する学生の卒業研究・特別研究の実施。 [PDF:160KB] |
| (2)原子力教授人材充実プログラム (6件) |
| 実施校名 | 実施年度 | 事業概要 |
| 名古屋大学 | H19 | 「技術コミュニケーション」に関する研究会への教員参加。 [PDF:129KB] |
| 大阪大学 | H19 | 原子力分野の教授養成講座を設置・開催(テキスト作成・講師招聘等)。 [PDF:195KB] |
| 京都大学 | H19 | 核燃料サイクル評価研究。教員による原子力産業・原子力政策の理解促進。非原子力系学生への原子力紹介。原子力関連会合への参加。 [PDF:144KB] |
| 福井大学 | H19 | 主に福井県内の原子力教育機関の教職員を対象としたセミナー「安全と共生の原子力人材充実プロジェクト」の開催(講師招聘等。) [PDF:264KB] |
| 福島工業高等専門学校 | H19 | 若手教員の国内原子力施設での研修及び国際会議での学会活動。 [PDF:148KB] |
| 八戸工業高等専門学校 | H19 | 教員による放射線挙動シミュレーションに関する知識と技術の習得により、原子力関連研究及び教育・指導能力の質の向上を目指す。 [PDF:139KB] |
| (3)原子力研究基盤整備プログラム (3件) |
| 実施校名 | 実施年度 | 事業概要 |
| 東北大学 |
H19~H21 | 大学所有のRI施設における計測・分析装置を強化充実して核燃料サイクル関連の学生実験を強化することにより、六ヶ所サイトのニーズに答える戦略的な教育研究活動を一層推進し、先進バックエンド研究を展開。 |
| 京都大学 | H19~H21 | 教育目的で使用する中性子線源の開発のための施設整備。JRR-4、HANARO(韓国原子力研究所)を含むKUR以外の施設・設備での研究・教育の推進。外国人研究者招聘による国際的研究・教育拠点整備。 |
| 東京大学 | H19~H21 | 原子力教育カリキュラムの充実(実験、実習を含む)。外部講師による講義の実施。国際的視野を有する教育の充実。原子力の長期ニーズに即したカリキュラム内容の改善・向上。高度原子力技術者としての質とスキルの向上を修了後にも継続して実施できる環境の整備。 |
| 6-② 経済産業省事業(詳細は、平成19年度経済産業省事業による) |
| (1)原子力教育支援プログラム (5件) |
| 実施校名 | 実施年度 | 事業概要 |
| 九州大学 | H19 | 「中性子の減速・拡散」や「中性子と物質の相互作用」などの原子炉物理・放射線計測実験演習及び関連する補助教材の開発。 |
| 東京大学 | H19 | 炉工学と核燃料サイクル工学の実践的な理解を図るための原子力専攻科目の教科書教材の作成等。 |
| 大阪大学 | H19 | 原子力実践教育コースのカリキュラムを構築するための基幹、実践教育の講義、原子炉シミュレータを用いた仮想実習及び教育用原子炉を用いた原子炉実習など。 |
| 東京工業大学 | H19 | 研究炉を用いた炉物理・炉工学実験カリキュラム及び核燃料サイクルの各工程に関する実験を通じての実践的な実習カリキュラムの構築。 |
| 北海道大学 | H19 | 炉物理実習教材、保全工学基礎強化プログラムの開発及び放射線計測やリスクの理解促進等。 |
| (2)チャレンジ原子力体感プログラム (11件) |
| 実施校名 | 実施年度 | 事業概要 |
| 東海大学 | H19 | 放射線の基礎知識・技術に関する講義、原子力施設の見学会、炉物理等の基礎理論実験の実施。 |
| 近畿大学 | H19 | 近畿大学を含む西日本を中心とした大学の学生を対象とした、近畿大学の原子炉を利用した原子炉運転等の実習及び研修会を開催。 |
| 東京大学 | H19 | 原子力発電所などのプラントの見学。研究機関が所有する大型施設を利用した実験・実習。電力会社の教育訓練施設を利用した実務的保修・保全実習、プラントシミュレーター実習等の体験教育。 |
| 京都大学 | H19 | 京都大学を含む全国数十大学に対して、全国共同利用研究所である京都大学原子炉実験所の施設を利用した実験教育。 |
| 大阪大学 | H19 | 原子力関連施設見学及び原子力国際インターンシップ。 |
| 武蔵工業大学 (現 東京都市大学) |
H19 | 研究炉等を用いた原子炉運転実習等。 |
| 東京工業大学 | H19 | 研究炉を用いた原子炉物理の基礎実験・実習。国際インターンシップ。日本原子力学会の大会への学生派遣等。 |
| 東京大学 | H19 | 海外大学におけるサマースクール等の集中講義への参加。 |
| 東北大学 | H19 | 原子力産業分野の実態の理解、原子炉基礎知識の習得、材料照射実験を体験させるとともに、実プラントに対する体験実習等。 |
| 福井大学 | H19 | 原子力関連知識・技術実習の場である「敦賀原子力夏の大学」の実施。 |
| 八戸工業大学 | H19 | 原子力発電所、再処理施設等での研修及び実習。研究施設における材料試験等の実習。 |
| 備考 : 東京大学については、研修・実習等の内容の見直しにより1本化。 |
| (3)原子力の基盤技術分野強化プログラム (6件) |
| 実施校名 | 実施年度 | 事業概要 |
| 東京大学 | H19~H21 | 蒸気乾燥器の流体関連振動に関する技術開発 |
| 東京大学 | H19~H21 | 機構論に立脚したより安全なハフニウム板型制御棒の開発 |
| 京都大学 | H19~H21 | 圧力容器溶接部の健全性評価法の規格・基準化に関する技術開発 |
| 大阪大学 | H19~H21 | ステンレス鋼レーザ溶接部の高信頼性化に関する研究 |
| 東北大学 | H19~H21 | 高Ni合金の高温水中SCC※機構解明と耐SCC成分設計に関する基礎的研究 ※SCC : 応力腐食割れ |
| 京都大学 | H19~H21 | 生体影響に視点を置いた新しい放射線防護体系の構築に関する技術開発 |
【評価コメントの一部】
<推奨意見>KUCA、KUR及び加速器等を用いた実験の基盤整備および、それらを利用した実験の教材も着実に
準備されたようであり、初期の目的は達成されたものと認められる。今後は、整備された装置等を十分に活用
して、参加者増員や実験費用低減等を含めた効率的な全国の学生教育に努め、原子力人材育成に貢献し続けら
れることを期待する。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>学生の理解度にも気を配り、実験の教え方、テキストの内容、実験終了後の学生同士の結果報告会、
討論会等のフォローが適切に行われ、着実に向上を目指した取り組みの結果、その効果が出ていると評価する。
今後も、学生からのアンケート結果等を考慮し、開発したカリキュラム・教材のさらなる改良を継続して欲しい。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>「国際舞台で活躍出来る原子力グローバルリーダー教育プログラム」との事業計画の下、領域横断
の実習・研究教育、英語でのデイベート、教職員の教育能力開発、国際連携強化と幅広い分野にわたり試行錯誤
の努力を重ね、概ね初期の目標を達成したものと評価出来る。その成果は、卒業生が未だグローバルリーダー
としては無理であるとしても真に国際舞台で活躍しているかであるが、卒業生の動向に関する情報を留学生も
含めて積極的に発信することが大切である。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>講義、講演会、セミナー、実習、実験、見学会など多彩な事業が行われたことは、評価できる。
今後も、特に低学年に対しては、できる限り多くの学生が参加できる機会が継続されることを期待する。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>大学との連携による実習・指導は、教員・学生への良い刺激になっている。
特に、学生にとっては、多様な学びの機会が提供され、原子力分野に進む動機となっているものと評価できる。
今後も、専攻科から原子力系大学院への受験者が維持されることを期待する。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>地域密着型の四国内の高専間、および原子力関連企業と連携する取り組みは、高く評価できる。
特に、高専間の連携は、成果の普及を図りつつ人材育成活動が行われており、教員・学生へよい刺激になって
いるという点でも評価できる。今後も、より一層、密接な連携を進め、教材や教育内容の充実を図って欲しい。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>東電福島事故の影響を身近な問題として取り上げて、キャンパス内の放射線を測定し、放射線の
人体への影響も含めて周辺住民にも公開したことは、正しい理解のために有効であったと評価できる。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>スキルノートを軸として、学生自身が、常に目標を見失わず、どのような授業・課題に集中して
取り組むべきかを考えながら、スキルアップをさせる取り組みは、大学としては斬新であり、良い試みである
と評価できる。今後も、継続しつつ、是非、中長期的な取組み全体の成果評価を行い、その結果を発表される
ことを期待している。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>地元の原子力関連企業の協力を得て、原子力発電への興味を持つ学生の裾野を広げ、より興味を
持つ学生に対して高度な専門教育を実施するという事業目的は達成されたと評価する。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>測定器の自作・展示・説明から地元施設の見学・実習、講義と非常に意欲的な内容であり、高専
のタイトなカリキュラムの中で色々な工夫をしながら、学生の側に自ら原子力・放射線を考える姿勢と能力が
しっかりと身につくようにプログラムの工夫をしながら人材育成を進め、原子力関連企業に就職する学生を多
く輩出するという実績を上げていることは評価できる。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>応用物理、機械、電気、材料、化学、土木、建築などの分野の学生に横断的に原子力に関する知識
を深めさせることは、正に原子力が総合科学技術であることを知らしめる上でも極めて重要であり、産業界との
連携による実践的教育を踏まえた教育プログラムを開発整備するという事業目的に対しても、共同原子力専攻
設置が成功したものと受け止められる。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>外部講師による広い視野からの講演、浜岡発電所における放射線管理実習等従前に比較し、大きな
進歩が読み取れる。今後とも、より実践的な浜岡発電所での実習を継続されることを期待したい。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>関係機関との連携を密にしつつ、全校を対象として本科1年から専攻科までの7年間にわたる一貫
した原子力関連のカリキュラムを開設したことは高く評価される。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>大学では少ない科目である保全工学を教員自身が学び、実習に必要な設備を整え、原子力プラント
の保全を教育課題の一つとして体系づけられた長年の努力は大いに評価出来る。保全工学に関する実践的知識を
有する人材の育成は、今後の原子力産業への人材供給のためにも極めて重要である。今後は、この成果を教育、
研究に生かして欲しい。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>原子力産業から離れた地域において原子力・放射線に興味を持たせ、原子力に関心を持つ学生が
増え、原子力産業界への就職希望者も増えたことは、本プログラムの成果として評価出来る。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>「ものづくり型原子力基礎技術者」という着眼そのものが素晴らしい。「ものづくり型原子力基礎
技術者」を育成するために、年次に応じた授業や非破壊検査等実務に役立つカリキュラムを導入し、プログラム
は予定通り実施され、非常に多くの学生がプログラムに参加し多くの他高専との情報交換が行われたことを評価
する。また、今後も継続して実施する予定であることは心強い。今後とも原子力関係の企業に就職する学生が
増えることを期待する。また、詳細な事業報告書が作成されており、他の高専へ大いに参考になるであろう。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>事業に期待していた教員養成大学の代表格として、原子力・放射線教育のカリキュラム、教材の開発
を行い、学生に対して、これを行うとともに全国の大学に広めることであったが、この期待に沿った完成度の高い
カリキュラム、教材が完成し所期の設定目標を達成したことは喜ばしい。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>健全性評価、原子力システム工学、システム安全工学、リスク学の基礎知識を有し、地域住民との
双方向コミュニケーションを推進しえるスキルを備えた技術者養成を目指した原子力技術者の育成と云う特徴あ
る取り組みについて、原子力システム安全・保全工学コース導入の検討・試行ができ、評価委員会でも妥当との
評価が得られたこと、各取り組みとも当初想定以上の参加を得ていることは大きな成果と言える。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>1年生から一貫し継続的に原子力を学ぶ機会と環境を整備した原子力教育を導入して、ほぼ確立した
体系が組めたことは評価出来る。また、今後も継続されることは喜ばしい。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>低学年向けの学生実験で放射線・原子力に関する基礎知識を身につけさせた後、学生の自立的な取り
組みにより放射線計測システムを自作させて弥生炉で実験する等学生の自発性を重んじた教育により、その後の
進路に好影響を与えていると評価される。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>文系、理系を問わず大学を卒業した者が放射線はただ「恐ろしいもの」との漠然とした認識しか
持ち得ないのでは、日本の教育レベルが問われることになる。今回のプログラムにより、少数の学生ながら
放射線に対する認識の転換が出来たとすれば、一つの進歩である。今後は、山梨大学の全学生(将来教員になる
教育学部の学生も大変重要である)の放射線・原子力発電リテラシーの向上を図ってほしい。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>多くの実験、実習を含むプログラムの実施により、学生の原子力に関する理解が深まり、国家試験
への多くの合格者も出した。放射線取扱主任者資格取得を目標に、学生の成長に応じたプログラムを体系的に
整備して行こうという姿勢は評価できる。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>「霧箱」を用いた様々な実験を開発し体系化する本事業は、放射線を実験的に理解する教育
プログラムの開発として評価出来る。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>原子力教育を5事業に分けて手際よく実施している。また、その結果の分析、反省点も的確である。
バラエティのあるプログラムの実施により、学生の原子力に関する関心を高めるのに成功している。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>放射線測定器や放射線測定回路を自作させ、科学展示会等で展示・説明させることで学生自身の
知識の涵養も図っていることは、学生の放射線・原子力に対する関心を高め、自信を持たせることに寄与して
いると伺える。エックス線作業主任者資格を取得させていることも原子力関連企業への就職にプラスに作用し
ている。総じて、事業の目的は的確に達成していると判断される。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>低学年生から高学年生に適したプログラムを用意し、全学年生に放射線・原子力に関心を抱かせ、
結果として原子力関連企業への就職学生数が増加したことは喜ばしい成果である。特に、参加者に限りはあるが、
原子力発電所における実習により、実習後の自由研究に積極的に原子力や放射線に関するテーマを取り上げ立派
な成果を挙げたことは、原子力の現場での実習の重要性を意味しており、今後も企業側も積極的に協力していく
べきことを示唆している。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>熱心な教員による低学年から放射線・原子力への興味の喚起、教育が多角的に行われ、また、
高学年ではインターンシップ、卒業研究等が的確に実施されている。これらの成果は、各種コンテストでの
受賞、原子力関連企業等への就職者数の着実な増加、東大等の大学院への進学に結実している。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>導入教育・事前教育を自学の教官で実施し、その後に、SNWや原子力機構の有識者による燃料
サイクル技術の実態説明を受けた上で、学生が研修先の選定を行うというやり方で、学生の負担がやや大き
いが、原子力専攻の学生であることから、原子力の専門分野を効果的に学んでいく方策を自ら設定していく
という方法は意欲的で効果的と評価。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>従来、放射線や原子力に関しほとんど教育して来なかった高専において低学年から学生に対する
啓蒙として原子力教育を取り入れたことは評価できる。また、これにより大学の原子力専攻への進学希望者や
選択科目の「原子力工学」の受講者数が増加したことは喜ばしい。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>放射線測定機器の導入や簡易型霧箱セットの購入により放射線・原子力教育基盤が構築され、
多くの学生に学習の機会が与えられた。今後、低学年から高学年までの体系的な放射線・原子力教育、研究
の実施が望まれる。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>中性子輸送計算や中性子実験の専門家が寡占化してきている状況下において、このような講習会
を催し人材を育成することは意義があったと認められる。今後、継続的なカリキュラムとして位置づけられる
ことを期待する。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>全学的に原子力分野に対する意識の向上、原子力産業の現状理解が進んだものと見受けられる。
特に、原子力発電所の見学、インターンシップは有用であったと思われ、今後もこれらを取り入れた低学年か
ら高学年までの一貫した教育が望まれる。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>大学、電力会社との円滑な連携により原子力体験型実習及び卒業研究を進められたことは、これ
までの実績に基づくもので評価出来る。これらにより、学生は高専では不可能な高度な装置を用いた実験や
得難い現場経験を積むことが出来貴重な体験となっている。また、近年の不況と原子力ルネッサンス時代を
反映したところもあるが、原子力関連企業への高い就職率は喜ばしい。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>6学部から成る総合大学の教養教育として「放射線入門」を開講し、学生がはじめて系統的に
放射線の基礎知識を身につけたことは評価出来る。また、同時に、放射線取扱主任者資格取得のための育成
プログラムも開始したことは適切な対応である。今後は、工学部において原子力に関する講義、実験等へ拡大
させるとともに、将来、小中高校の教員を目指す学生に対しても放射線・原子力を正しく教えられるよう学習
プログラムを構築されることを望む。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>原子力人材の育成について、四国地域における高専間連携とキャリアパスの明確化という観点
から入っていこうとしている点は、評価できる。難しい問題は多いと思うが、これまで培われた四国地域内の
連携基盤の上に、産業界の協力を得て、四国地域らしい原子力人材育成体制が整うことを期待する。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>地域ネットワーク構築や地域協働型原子力教育システムのプラットフォームの構築、双方向
コミュニケーションに関する講演などによる活動が適切に実施されたと考える。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>原子力導入教育プログラムは、付属高校と連携することで、高校段階での放射線・原子力に対する
知識レベルを把握し、1年次の学生がスムーズに原子力専門教育に入って行ける教育内容と入学後の学生の成長
プロセスを踏まえて、学習補助教材の作成(ウェブ活用)、体験型原子炉試験の構築をするとともに、教員人材
の育成が着実に実施されている。このことは、2010年度スタートの「原子力工学科」に活用されるとのことで
あり、当初の計画目標を概ね達成していると評価でき、今後の活動と、この取組みの成果に期待している。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>福井県内の原子力関連組織の放射線安全について、中核的に活躍する人材育成を目的とし、原子力
技術応用工学科の中に放射線安全専門職育成プログラムを構築し、地域事業者が求める人材育成手法を確立した
ことは、成果をある程度挙げつつあり、今後の発展を期待している。また、この課程で外部の関連有識者の意見
を的確に取り入れ、また、類似の外国の大学の事例と詳細な比較検討も行っていることは普遍的な価値を生み出
すと思われる。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>大学の原子力教育ではまだ取り組みが十分でない保全工学に関して、「産業界の要請に応えた
実践的な保全工学に関する人材育成」という目標を設定し、全学教育を通して系統的な戦略を立て、成果を
挙げたことは評価できる。特に、学生に保全の重要性を認識させ、結果として原子力産業を目指す学生を
増やした取組みは、目標を達成していると考える。今後のプログラムの進展・充実に期待する。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>H20年度に「核燃料サイクル実験」カリキュラムを完成させ、H21年度に正式科目(単位化)
としてカリキュラムに取り入れ、さらに実験テキストも公開されており、良好な活動成果が報告されている。
集中講義型から、定常講義型に組み替えることが出来たことは、今後の継続的な人材育成の素地が出来たと
評価できる。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>原子力工学専攻を持たない大学・大学院において、いかなる原子力教育を実施すべきなのかと
いう課題に対する一つの雛形を構築したという点で評価できる。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>低学年(1~3年)では講演や施設見学で原子力の基礎知識を理解させ、高学年(4、5年)では
講義、インターンシップや卒業研究で知識と意識レベルを発展させるカリキュラムとなっている。高専5年間
での一貫した原子力科目を開設し、幅広く原子力への関心を抱かせ、知識を習得させる工夫がなされたことは、
今後の教育の根幹となるもので大きな成果と考える。また、運営評価委員会による継続的な改善の仕組みが
機能していること、成果に対する分析と今後の活動方針がしっかり検討できていると考える。以上のことから、
本事業は高専における原子力分野の人材育成プログラムの良好事例と評価できる。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>プルサーマル炉心設計や長期サイクル炉心経済性評価などの解析コードが整備され炉物理関連の
知識修得ツールの強化が図られている。さらに、これらを活用したカリキュラムも整備されたため、目標とし
ていた、炉心管理の中核人材を育成する方策が完備できたと評価できる。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>当初計画通り、理学部2、3年向けに「総合原子力科学プログラム」として9科目が開設され、
大幅に予定を上回った学生が受講しており、学生の関心の高さ、教員側がそれに応えようという姿勢も随所
に覗えることから、当初の目標はほぼ達成できたものと評価できる。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>平成20年度、平成21年度を通じて、新設した原子力安全工学科の教育体系の整備(実験テキスト
の作成)、実験装置の整備(実験機器の購入)ができた段階であり、今後の人材育成活動とその成果に期待する。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>核燃料サイクルのバックエンドに関する教育について、地元企業の関係者との連携により、
①サイクル教育の強化・講義/実験の必修化、②産業界ニーズを踏まえた研究の推進、③国内外会議での
発表・海外大学との連携研究を実施するなど、有効な成果が確実に得られるよう配慮されたプログラムは
評価できる。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>原子力人材育成において学生実験は教育を効果的に実施する手段として最も有効なものであり、
特に原子炉実験は原子力技術修得に非常に貴重なものであると考える。本プログラムにより、①核物質防護
施設の整備を終了し、KUCA、KURを用いた学際的原子力科学に関する共同利用・共同研究及び教育を推進
できる環境が整ったこと、②世界に先駆けて加速器駆動未臨界炉実験の成功に寄与し、その基礎研究ができる
場を樹立できたこと、③非常勤研究員の配置によって原子力基礎科学、粒子線物質科学、放射線生命工学に
関する研究が進展するなど、学際的な原子力研究・教育の活動拠点としての環境が整備され、成果が上がり
始めていることは評価できる。今後も原子力分野の人材育成が順調に推進されることを期待する。
詳細はこちら
【評価コメントの一部】
<推奨意見>我が国の原子力人材育成のトップを行く先導的教育として、非常に高いレベルで事業を進め、
産業界や研究機関の協力を得る仕組みを完成させ、カリキュラムの充実のための数々の仕組み(運営諮問
委員会、教育会議、修了生からの意見聴取などによる)を実施したことは評価できる。また、人材養成の
成果についても、期待通りであった。本教育は、我が国の原子力人材教育のBest Practiceと位置づけられ
るものであり、この成果を他の大学でも参照し、学べるように成果が公開されることを期待する。さらに、
今後、本分野での国際的視野の重要性はさらに高まると考えられるため、そういった観点から検討される
ことも期待する。
詳細はこちら