パネル討論概要
<はじめに>
(松井)
田中先生から今までのシリーズセミナーの概要と先生のお考えを、ラクソネンさんからは、フィンランドにおける原子力安全の実際のプロセスからの話を伺いました。今までの議論が非常に幅広いものになっておりますが、まず、スライド (注) に示す論点から議論していきたいと思います。
(注)「論点」として示されたスライド:
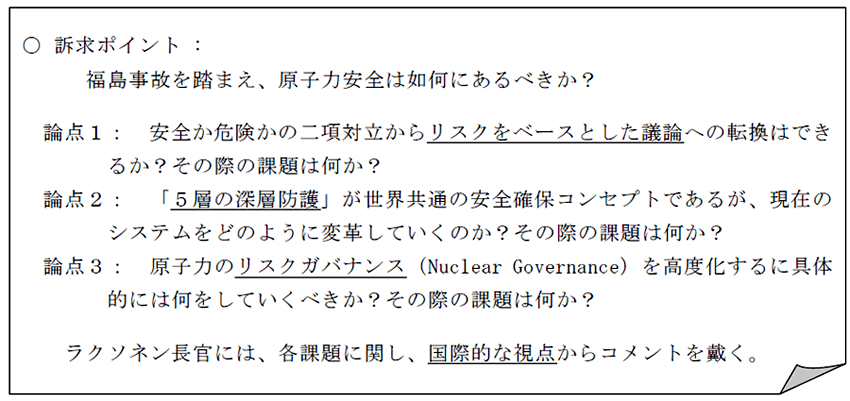
| コーディネータ: | 松井一秋((財)エネルギー総合工学研究所 理事) |
| パネリスト : | 田中 知(原子力学会会長、東京大学大学院教授) |
| J.ラクソネン(フィンランド放射線・原子力安全庁長官) | |
| 田村昌三 (東京大学名誉教授、元安全工学会会長) 田村氏経歴
田村昌三(たむら・まさみつ)氏 東京大学名誉教授、元安全工学会会長 1969 年東京大学大学院工学系研究科燃料工学専門課程博士課程修了、 工学博士。1990 年東京大学工学部反応化学科教授。化学システム工学専 攻教授、新領域創成科学研究科環境学専攻教授を経て、2004 年定年退官。 名誉教授。2009 年横浜国立大学安心・安全の科学研究教育センター教授 任期満了退職。日本学術会議安全工学専門委員会委員長、火薬学会会長、 安全工学会会長歴任。専門はエネルギー物質化学、化学安全。 |
|
| 谷口武俊(東京大学大学院 客員教授) 谷口氏経歴
谷口武俊(たにぐち・たけとし) (財)電力中央研究所 研究参事、工学博士 東京大学 大学院工学系研究科原子力専攻 客員教授 特定非営利活動法人HSE リスク・シーキューブ代表理事。日本リス ク研究学会理事、大阪大学大学院工学研究科特任教授を歴任。著書に『リ スク意思決定論』(単著、大阪大学出版会)、『どうする日本の原子力- 21 世紀への提言』(共著、日刊工業新聞社)などがある。 |
田中先生から今までのシリーズセミナーの概要と先生のお考えを、ラクソネンさんからは、フィンランドにおける原子力安全の実際のプロセスからの話を伺いました。今までの議論が非常に幅広いものになっておりますが、まず、スライド (注) に示す論点から議論していきたいと思います。
(注)「論点」として示されたスライド:
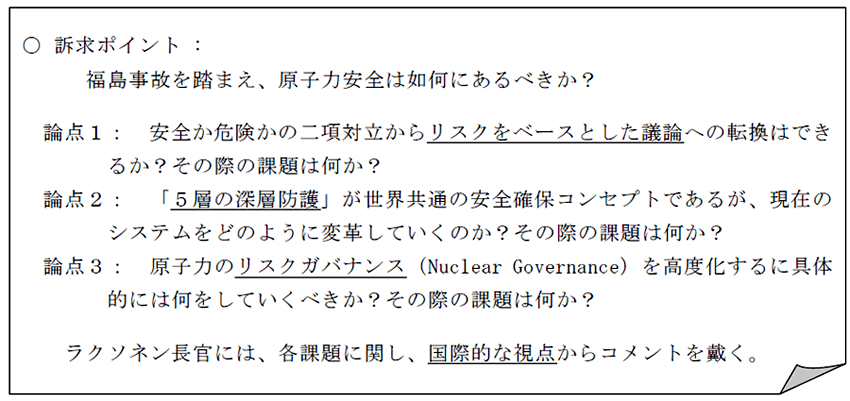
| <論点1: | 安全か危険かの二項対立からリスクをベースとした議論への転換はできるか?その際の課題は何か?> |
リスクを安全の議論に持ち込むという考えもある一方、リスクを持ち込んだ議論には短所もあるとも思いますが、皆様の考え方を伺いたいと思います。
リスクとは、あることが、ある確率で起こり、その時どんなハザードがあるかを議論するものとした時、相対的に使われることが多いと思います。どんな概念でも、何が出来るかより、何ができないのか、判らないのかを明らかにしつつ使うことが大事と思います。
原子力事故のように確率が小さくても起こると被害が大きいものは、普通のリスク概念ではうまく評価できないものもあります。リスク概念の限界を考えつつ、どう使えばいいかが分かり易く表せるようになっていけばいいと考えています。
化学産業の分野でもリスクという言葉を使うことが多くなってきました。発生確率と影響度の二つの概念でリスクを考えますが、原子力では、特に確率が低いが影響度が大きい事象の取扱いが重要な問題です。リスクゼロはあり得ないため、いかに低減できるかが問題となります。システムのが複雑化、不確実化、曖昧化を考えると、リスク低減のためには、関係者が情報を共有し、十分な議論を行うことも必要です。そして、関係者がそれぞれの立場で共にリスク低減に貢献していく仕組み作りも重要です。
学問の分野でもリスクの定義はさまざまです。例えば、リスクが高いという表現は因果関係に、また、リスクが大きいという表現は効用に着目したものと思われます。
「二項対立からリスクをベースとした議論への転換」は、できると思っています。極にいる人は別にして、中間的立場に立つ多くの人々を信頼し、パートナーとして話をしていけば、確定した世界に生きているわけではないと理解してもらえると思います。地域社会の人とは、同じ土俵の上でパートナーとして思わないと話はできません。
まずは組織の中で議論ができるようにならないと、外部と議論はできません。組織内で議論する中でステークホルダーが見えるようになると、対話ができるようになります。組織の中に二項対立的なことが起きるようではだめと言えます。
ラクソネンさんの講演では、リスク、確率の話が明示的には出ていないように見えましたが、お考えはいかがでしょうか。
確率論のアプローチは規制の中で明示的に示されますが、数字でリスクが十分小さいと説得するわけではありません。リスクの定義、公衆への説明が難しいのはフィンランドでも同様です。原子力には低いリスクが強く期待されるからです。科学的な議論を基に、リスクは受容可能であることを説得する必要があります。
人々の安心感は重要です。科学的な議論だけでは安心感をもたらすことは必ずしもできません。議論を行い、人々が感情的に理解できるようにすることが重要です。
放射線防護に関するリスクと原子力のリスクは分けて語る必要があります。放射線被曝のリスクに関しては、高線量の地域に住むと、どういうリスクが具体的にあるのかを理解してもらうことが必要です。我々のアプローチは、追加的な被曝と通常のバックグラウンドの被曝の変化を比べる方法で行っています。土壌からの放射線によって一定の被曝はあり、地域によって異なります。チェルノブイリ事故後の降下物もありましたが、それよりも自然放射線が大きく、フィンランド国民の約5%はラドンにより年間10mSv被曝する家に住んでいます。放射線は生活の一部であり逃れることはできません。どこまで許容するかの問題であり、通常の変動範囲以上の被曝がなければそれ程心配ないと説明できます。
原子力安全に関して人々に明らかにすべきことは、完全な安全はなく、確率が小さくても事故の可能性は残るということです。事故をどのように回避するか、どのように起きるか、事故の影響はどうか説明することが肝要です。
日本では、今回の事故で誰も死亡していないこと、大量被曝もないことを国民が理解すべきです。人々に対するリスクとしては地震・津波自体の方が高く、事故防止に何が必要かの説明をした方が理解し易いということです。規制に対する信頼性の醸成も重要です。
谷口さんの話の中で「組織の中の議論が重要」と言った場合の、「組織」とは小さなものを念頭に置いての話ですか、それとも社会といったレベルまでを考えてのことですか?
例えば、電力会社、発電所、もっと小さなグループといったようなものです。
| <論点2: | 「5層の深層防護」が世界共通の安全確保コンセプトであるが、現在のシステムをどのように変革していくのか?その際の課題は何か?> |
論点2に関して、手順としてどう考えているか、どこまで保証すれば炉心溶融を防げるか、その手順を示せるのか等に関して、もう少しお話頂ければありがたいのですが。
炉心溶融防止のためには、臨界の制御、除熱といった基本的な性能の確保、安全系システムの保護が必要です。信頼性向上には、崩壊熱除去の安全系に冗長性を加えることです。新しい炉では、いずれの1系統にも十分な性能を持つ4つの系統が、それぞれ分離して設置されており、個別に保護されています。最近の要件として、安全系の多様性が求められます。原則は昔からありましたが、体系的に実施されるようになったのは最近です。相互の依存性がないことを主眼に規制当局も検査するようになっています。
福島第一事故後の追加ですが、電源の信頼性に関し、既に4つのディーゼル発電機が設置されていますが、より小型のディーゼル発電機、ガスタービン発電機も要求しています。また、電力がなくても崩壊熱が除去できるというもの要件も加えています。
専門外ですが、原子力の「5層の深層防護」の考え方は良く理解できます。化学産業の場合は、暴走反応を制御するための最後の手段として、多くの場合、反応物を大量の水の中に落として反応を停止させるような設計になっています。また、火災発生時には消火活動を行い、化学物質の漏洩のおそれがある場合には、適切な情報を提供し、化学物質による被曝を抑えることに努めております。4層まではプラントの設計レベルで対応すべきものですが、5層目は事業者と公共、消防、住民とが協力して防ぐものと思います。
福島第一事故を見て思うことは、前段否定の論理は、前段がかなり完璧に近いことが前提であるべきですが、今回、そうなっていたかの検証が必要と思います。深層防護は工学システムとして洗練された考え方ですが、本質的な弱点を見逃すことがあり、深層防護の誤謬もあります。最終的に人間の果たす役割は大きいと再認識すべきです。
5層目は緊急時対応で4層までとは異なりますが、4層目と5層目は繋がっています。どうやって繋げていくかが課題です。重なり合いと相互分担の考え方について、しっかりした議論が必要です。
WENRAの Safety objective の4層目と5層目はかなり異なります。4層目はプラント設計に係る部分で、目的は、全ての手段で閉じ込めていく、放出がないようにしていく、周辺に影響がないようにしていく、あったとしても限定的にしていくというものです。WENRAに明確には書かれていませんが、緊急時対応が5層目で、各国が個別に対応している部分です。まだ発行されていませんが、8つのポジションペーパが準備中で、冊子を来年11月に発行する予定です。
5層目に関し、フィンランドでは明確な要件があります。重要な例として、プラントから半径5kmでは4時間以内に住民が避難できるようにという時間的な制限があり、プラント近くに住める人の数を制限しています。避難経路に関する要件などもあります。
5層目の緊急時対応の中で、事業者の責任、役割をどう考えられているのでしょうか。
事業者の役割と、自治体や政府の役割には明確な違いがあります。
事業者はプラント安全性に関する責任があり、放出を最小限化していくことです。規制側から特別に許可を得る必要はありません。炉心損傷防止や閉じ込めは、事業者しか適切な判断はできません。自治体あるいは政府の責任は住民の安全を守るということです。救援措置や避難措置は、電力会社の役割ではありません。
福島においては、ちゃんとした計画が無かったにもかかわらず、きちんと避難が行われ、チェルノブイリと比較して、はるかに良い結果になったと思います。
オンサイト・マネージメントという観点からからは、私もそのようなことと思いますが、社会はそのように見てくれたかと疑問は残ります。
少なくともフィンランドにおいては、社会がそのような疑問を呈したことはありません。現場の人間が、その時何をなすべきかとの判断を最も適切に行えるのだと思います。
日本として新しい規制概念となるので、規制システム全体がシステマティックで分かり易いことが必要です。規制改革をどの程度のスピード感でやっていくのかも大事な点です。
フロアから「WENRAでは避難に関し定量的な基準値を設定していますか」との質問を頂いています。
重要なクライテリアは、閉じ込めの健全性を維持することです。どんな状況であってもというと難しくなりますので、例えばセシウムにおいてはトータル100テラベクレルの放出を越えないというのが限界値です。あらゆる手段を講じて閉じ込めの健全性を守ることができる限りWENRAの目的は達成できることになります。哲学的な、概念的な目的であり、ターゲットを示すものです。できる限り健全性維持するということです。
| <論点3: | 原子力のリスクガバナンスを高度化するに具体的には何をしていくべきか?その際の課題は何か> |
リスクガバナンスは前回の討論会でも取り上げられましたが、フロアの反応は、有意義な議論と言う方と、よく分からないという方とに分かれる結果となりました。リスクガバナンスと原子力の安全をどのようにまとめるかについて意見を頂きたいのですが。
プラントの安全確保には保安基盤と安全文化からなる保安力という考え方が重要と考えています。安全管理をコアとする人・組織、設備、技術、マネジメントの体系としての保安基盤と、それを活性化する人間行動、組織活動、事業所環境が安全文化です。平常時はもとより、異常時においても、原子力のもつ揺らぎのあるリスク、確率は低いが影響度が大きいリスクにおいて、確率のや影響度の低減には安全文化が効果があるのではないかと考えます。
トップが安全の方向を示し、現場がモチベーションをもって安全確保に向けて活躍できるように機能するマネジメントが必要です。リーダーシップ、トップガバナンスが重要です。
ガバナンスという言葉を使ったのは、適正な仕組みを欠いていたから起こったとの問題意識からです。原子力の抱えている問題の解決には、仕組みを変えていく努力が必要と思います。日本の原子力事故が技術的安全管理の問題でなく、社会的信頼の喪失、社会的拒否となっているとの認識からです。ガバナンスという言葉を用いないとすれば、狭い意味でのリスク管理でなく、社会的リスク管理となると思います。
今回の福島の復興および除染において、中央と地方の問題が顕在化しているように思えます。中央が動かないとできないという構図となっており、復興の動きが遅くなっています。技術的には英知を集めればいいが、社会に落としこんで実際に技術を利用することを考えた場合、中央と地方の関係も含め考えさせられる面があります。
フィンランドでは分権の状況はいかがですか。
原則として、原子力が必要か否かは政治的指導者が決定します。新しい施設は政治判断です。政治判断後は、安全性は組織に任せます。決定の前には社会で議論を行います。
有益か否かの政府の判断は議会で議論します。議会の委員会では専門家の意見を聞いて、議論し、意思決定を行います。決定がなされると議論は終了で、後は専門家に任せることとなります。規制当局が安全を確認できれば、議会は建設許可を出し、政府が決定します。
運転に関しては、運転主体と規制当局の間で処理されるものとなり、政治家は距離をおきます。政治家は原子力の必要性の決定に関与しますが、その後は介入しません。
基調講演のリスクガバナンスに関する箇所をどのようにまとめるか、悩みました。組織のリスク管理と社会のリスク管理とに分けることも考えましたが、原子力の場合、さまざまなリーダーがおり、大きな形でのガバナンスもあるかなと思い、今回提示したような案となりました。
リスクガバナンスのコアな部分は社会的リスク管理のフレームワークと思います。さまざまなステークホルダーが関わることが重要であり、さまざまな価値判断が入ってきます。多くのステークホルダーと議論する仕組みをどう作るかを考えることが重要と思います。
フロアからですが、「最悪シナリオとして、どこまで考えればいいか」という質問がありますが、この件に関していかがですか。
軽水炉の場合、今回の福島は最悪に近いかもしれません。科学的技術的に想定し得るものが、本来の最悪シナリオと思います。
福島第一事故は特別な事故ですが、ある程度の予測はできたと思います。津波が起因事象となることは想定していなかったかもしれませんが、東京電力や他の組織の予測を見ると、ある程度シナリオの可能性は確認されていたと思います。崩壊熱除去機能が喪失して、格納容器が破損して、アクシデントマネジメントでは十分に対応できない状況でした。
深層防護の4層目は、予め想定できない状態に対して緊急事対応策をとらなくてはならないものです。5層を活用して不測の事態に対応していくことが重要になると思います。
フロアからの質問ですが、平時の取組みと人材育成に関してはいかがですか。
「5層の深層防護」の考え方は立派なコンセプトであり、その実践が大事と思います。プラントの安全確保のためには、保安力という考え方を機能させていくことが重要です。システムだけではカバーできないもの、リスクの揺らぎ、確率は低いが影響度の大きいリスクへは安全文化で対応する必要があると思います。また、緊急時における被害低減のためには、事業者の漏洩拡大防止対応はむろんのこと、事業者、行政、国民のリスク情報の共有化と適切な危機対応が重要です。
リスク低減の仕組みを機能させるためには、それに係る人材育成が重要です。プラントの安全確保、リスク情報の共有化や危機対応等においては、安全技術者や安全の専門家の育成が必須であり、また、リスク情報を理解し、適切な危機対応行動をするためには、国民がも安全に対する基本的考え方をの理解し、基本的な安全知識をもつことが必要です。
そのためには初等・中等教育、高等教育、企業教育、社会人教育等各段階に応じた体系的な安全教育プログラムが重要であると考えます。
フロアからの質問ですが、炉心溶融後の再臨界に関しコメントお願いできますか。
少なくとも福島の場合は再臨界起きていません。炉心損傷の後、中性子吸収材料と炉内構造物が相互作用を起こすことから再臨界のリスクはさらに軽減されると思います。計算しても明確に兆候の説明がつき、再臨界の兆候は見られていません。フィンランドでも計算していますが、計算した通りの様子が見られています。
受動的安全性(パッシブセーフティ)が取り上げられました。フィンランドでは、パッシブセーフティはどの程度の重きをおかれているのかお聞かせ願えませんか。
特に崩壊熱除去ということで重要性は増しており、設計の中ではパッシブにやっていくことを盛り込まれています。新型炉の場合には、三菱重工、東芝から提案され、非常によいものが作りこまれています。EPRの設計には入っていませんが、話し合いをして新しいEPRに盛り込まれることと思います。
「冷やす」については、そういう概念も必要と思いますが、効果的に働く能動的なものとの組み合わせもあっていいのかと思います。パッシブセーフティだけでいくと、原子炉のパワーの問題でてくるので、それがいいのかの議論も重要と思います。
フロアで他に御意見あればお願いします。
安全目標の話がありませんでしたが、いろいろな産業間のつながりを含め、全体を見る国の組織があれば教えて頂きたい。
そういう組織はないと思います。ご質問に関連しては、10年以上前リスク学会で、共通にできないか議論したことがありました。しかし、その当時は、決めたとしても、産業により成熟度が違うという議論があり、深化しなかったと思います。
本件は、さまざまな要素が関係する難しい課題であり、問い続けていく問題と思います。
谷口さんが言及されたものは、平成15 年頃に原子力の安全目標について中間報告されたものと思います。一方、ラクソネンさんが引用されていたものは、WENRAの新設炉に対する安全目標に関するものです。
最後に、講師の皆様から、言い残したこと等何かございましたらお願いします。
安全目標については、他の分野の事故リスクのデータはどの社会にもありますが、このリスクは、参考値として用いることはできないでしょう。
原子力安全に関しWENRAで行われている議論は、数値的ゴールを目指していませんし、そういう役割を担ってもいません。原則として安全は合理的にできるだけ高いものでなくてはなりません。決定論なアプローチでない、深層防護というあらゆることをしてさまざまな枠組みの中で安全性を担保していくものです。
それとは別に、数字的な計算はそれほど重視していません。絶対的な数値ではないからです。限界がある数値です。確率リスク評価方法論は、そういう目でみる必要があります。
本シリーズセミナーの副題である「巨大技術は制御できるか」というのも気になっております。技術な観点では制御できるし、制御しなくてはいけないと思いますが、実効化していくには技術と社会の関わりと行った点が、課題としてがあると思います。
どこに問題があるかを見極めつつ解決していかないと、前へ進めないと思いますし、そういう時期にきているとも思います。どこに本質があるかを見極めつつ、一歩でも前に進めることが必要かと思います。
本シリーズセミナーを行ってきて、ある種の方向性は出てきたと思います。今後、ここで行った議論を具体的にどう活用していくかが重要です。本セミナーを契機にここでの議論が社会に受け入れられるものとなればいいと思います。
当研究所では、20年以上前、「巨大技術の安全性」という本を上梓しました。それから四半世紀たち、今回の事故があり、社会も変化してきて、このたび7回に渡り皆様と議論させて頂きました。
現状で、これだというものが必ずしも見えていませんが、リスクやガバナンスという見方で全体を捉えていくという方向性、原子力安全については、リスク低減の努力をしつつ制御していくことに確信がもてるような気が致します。これについては、今後いろいろな努力がいるとは思います。